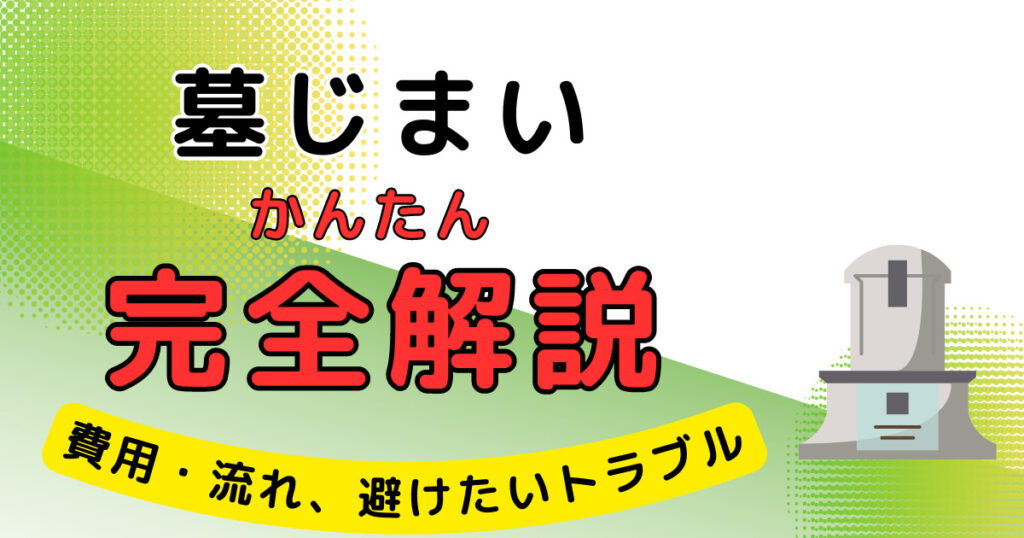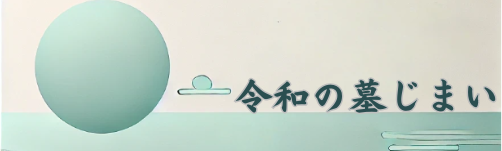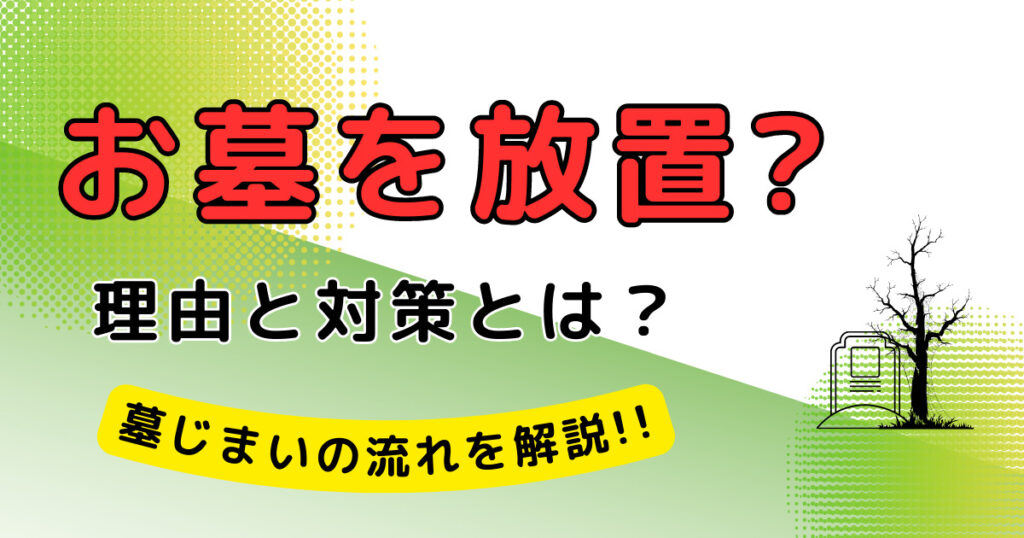ヒビだらけで崩れそうなお墓
雑草に囲まれて姿が見えなくなったお墓
お墓参りに行ったとき長年放置されているお墓を見た経験はありませんか?
厚生労働省の調査データ(衛生行政報告例)によると、無縁墓の改葬(墓じまい)が行なわれた件数はここ10年で約2500~7500件(年間)。
改葬されていないお墓を含めると、全国で数万件以上のお墓が放置されていると考えられます。
ではなぜ、お墓は放置されてしまうのでしょう?
本記事では、「墓じまいせずお墓が放置されるとどうなるか?」を解説したうえで、お墓が放置される理由や墓じまいの流れも紹介します。
(スポンサーリンク)
【結論】墓じまいしない=可|しかし、お墓の放置はリスク大
「墓じまいしない」という決断はまったく問題ありません。
ここで、認識しておいてほしいのは下記2つのポイント。
- 墓じまいしない(お墓を維持)
-
管理費をおさめ、区画を清掃し、法要を続ける。承継者と連絡先が明確。
- 墓じまいしない(お墓を放置)
-
管理費を払わない、雑草・外柵破損をそのまま放置、連絡不能。
通知→掲示→公示ののち、無縁仏として合祀・撤去の可能性があります
墓じまいしない(お墓の維持)をえらぶケースの最低ラインは下記3点です。
- 管理費を今後ずっと納付できる
- 承継者が決まっており、連絡もできる状態にある
- お墓参りなどで簡単な清掃・点検を継続できる(雑草・外柵・危険箇所)
上記ポイントが問題ないようでしたら、墓じまいしない選択肢は問題ありません。
(スポンサーリンク)
墓じまいしないで、お墓を放置するとどうなる?

墓じまいしないでお墓を放置するとどうなるのでしょう?
結論からお伝えすると、放置されたお墓はやがて解体されてしまいます。
放置されたお墓が解体されるまでの流れは以下の通りです。
管理費の支払い通知が発行される
お墓が放置されたからと言って、すぐに解体・撤去されるわけではありません。
まずはお墓のある寺院や霊園からお墓の管理者へ、管理費の支払い通知が発行されます。
(入金がない場合)お墓に立札が建てられる
管理費の支払い通知はお墓の管理者に届けられますが、多くの場合、入金が滞ってしまいます。
納付期限までに入金がない場合、放置されたお墓に立札が立てられ、官報に名義人が公示されます。
墓石が解体される
管理費の支払い期限を経過し、さらに一定期間連絡がない場合、強制的にお墓から遺骨が取り出されます。
さらに、墓石自体も解体・撤去され、墓地が更地に戻されます。
墓地は墓地管理者(寺院や霊園)に返還され、お墓は跡形もなく無くなってしまうのです。
なお、引き取り手のない遺骨は合祀墓(ごうしぼ)に埋葬されます。
(スポンサーリンク)
お墓が放置される理由【4選】

お墓が放置されてしまう理由を4つ紹介します。
高齢になりお墓参りできない
高齢になるとお墓参りに出かけるのも大変ですよね?
お盆やお彼岸など、猛暑の時期に行われるのがお墓参りです。
お墓まで行けたとしても、40度近いなか墓石の掃除までできないことが多いです。
暑さや体力の問題にくわえ、行動範囲が制限されることもお墓参りのハードルを上げています。
運転免許を所持しているうちは自家用車で移動できますが、高齢になると免許を返納するケースも増加しています。
このように、高齢になることでお墓参りができなくなり、やがてお墓が放置されはじめるのです。
お墓が自宅から遠い場所にある
お墓が遠方にあるため、やがて放置されることも多いです。
お墓が自宅近くにあれば問題ないですが、多くの方が帰省から墓参りまで1~2日かかるのが現実。
また、海外在住の方は、お墓参りのために一時帰国するのはハードルが高いです。
このように、自宅とお墓の距離が遠いと、健康上の問題がない方でも大きな障害となるのです。
お墓を建てた祖先は、子孫が地元から離れることを想定していません。
時代の流れがあるので仕方ないことですが、、、墓地の立地が障害となりお墓が放置されることは多々あるのです。
お墓の管理費が負担になっている
お墓の管理費は、年間1万円ほどが平均といわれています。
お寺の檀家になっている方は、地域や宗派によって1万円以上の費用を支払っている方もいます。
年に一度の支払いとはいえ、お墓の管理費を負担に感じている方も多いのが実情です。
お墓の後継者がいない
お墓の後継者がいなくなったらお墓が放置されることが確定します。
実際、日本の人口減少にともない、後継者不在で放置されてしまったお墓は急増しています。
後継者がいなくなる理由はさまざまです。
- 独身で兄弟姉妹に子どもがいない
- 子どもはいるが実家のお墓を継ぐ気がない
- 親戚のほとんどが故人となってしまった
もう一度お伝えしますが、後継者がいない場合、お墓は将来的に放置されます。
ご自身が存命のうちに、墓じまいすることを検討した方がよいでしょう。
(スポンサーリンク)
墓じまいすべき【3パターン】お墓を放置しないで!

墓じまいするべき3つのパターンを紹介します。
該当した方は、将来的にお墓を放置してしまわないように注意してください。
お墓の管理が負担に感じる
お墓の管理を負担に感じていませんか?
負担を感じる理由が健康面だとしても経済面だとしても、なるべく早めに墓じまいの準備を開始した方がよいです。
墓じまいにかかる費用や手間を考えると、面倒になってつい先延ばしにしがちです。
しかし、問題を放置して1年、3年、5年と経過すると、状況はさらに悪化します。
いまのうちに墓じまいを検討することをオススメします。
子どもに迷惑をかけたくない
「わが子に面倒なことを押し付けたくない」と考えたことはありませんか?
お墓がある限り、毎年のお墓参りや維持・管理費用は永久的につづきます。
将来的に子どもに迷惑をかけないように、自分が元気なうちに墓じまいを実施する人も多いのです。
お墓の後継者が不在
晩婚化や子どものいない家庭の増加で、お墓の後継者がいないケースも増えています。
「一人っ子で兄弟姉妹がいない」
「おじやおばなどの親戚がすでに亡くなっている」
「子どもはいるが実家を出て独立しており、別の場所にお墓を建てている」
このように、自分の代でお墓の管理者が途絶える人もいるでしょう。
後継者がいないとわかっているなら、今すぐにでも墓じまいを検討すべきなのです。
(スポンサーリンク)
墓じまいしないとどうなる?|よくある質問
墓じまいをせず放置すると、遺骨はどうなる?
お墓を放置すると、規約に基づき無縁仏として合祀される可能性があります。
お墓の管理費を払えなくなったらどうすべき?
まずは管理者へ相談してください。放置はNGです。
お墓の承継者がいません。お墓の維持を続けて大丈夫?
短期的には大丈夫ですが、長期的には改葬を検討したほうがよいかもしれません。
判断に迷うときは、家族親族の同意を得て、費用負担や価値観をすり合わせてください。
寺院との関係が不安です。どう話せばいいですか?
「お墓の規約と費用の内訳を教えてください。家族に説明するため、書面やメモで残したいです」と落ち着いて要点確認しましょう。
もし離檀交渉に困ったら、代行業者に依頼することも視野に入れてください。
墓じまいするかどうか、どのタイミングで検討すればいい?
お盆・お彼岸や年末年始など、親族が集まりやすいタイミングで検討・話し合いしてください。
(スポンサーリンク)
墓じまいしないとどうなる【まとめ】放置はNG!管理するならOK

本記事では墓じまいしないとどうなるのか?放置や無縁仏のリスクといった観点から解説しました。
お墓を放置すると、待っているのは無縁仏。
今後ずっと管理し続けられるならよいですが、もしお墓を管理できないなら、墓じまいを検討するのは悪いことではないです。
もし墓じまいについて迷っているなら、下記記事で墓じまいのことをわかりやすく解説しているので、ご一読ください。