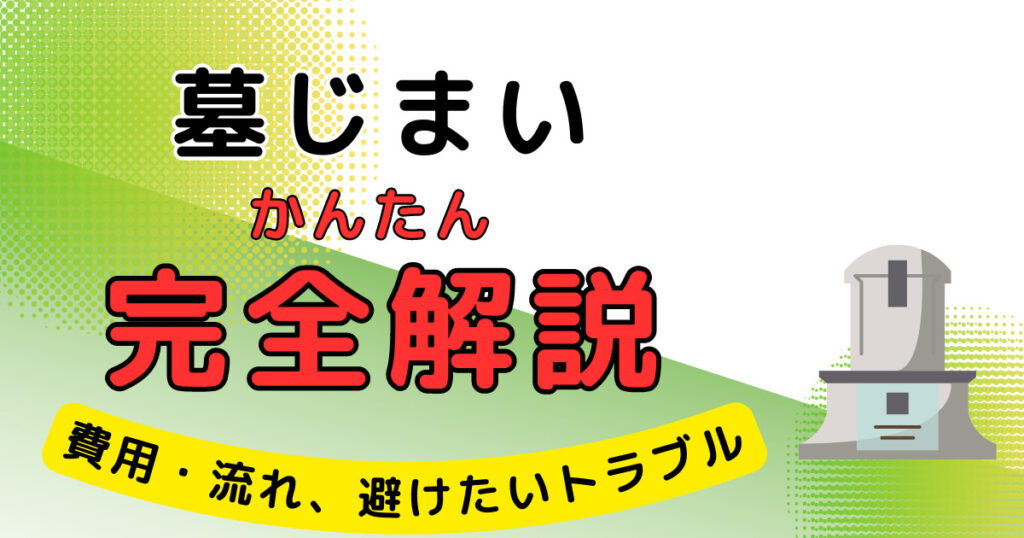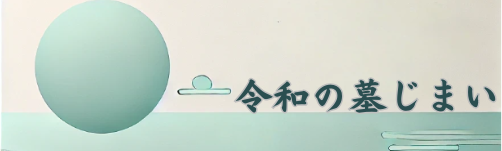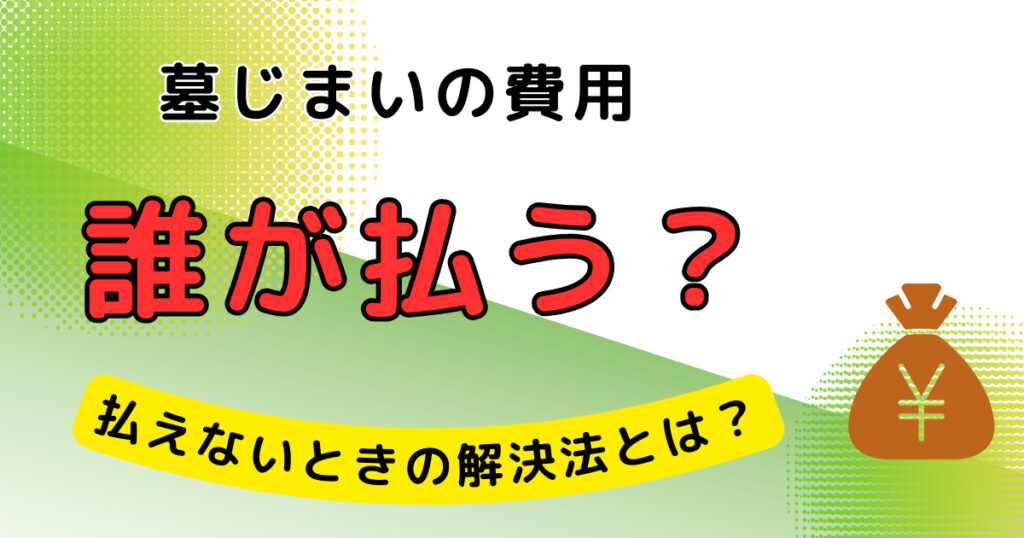墓じまいの費用って誰が払うの?
墓じまいでもっとも揉めやすい”誰が費用払うの”問題について解説します。
>>墓じまいとは?費用や手続き・流れ、トラブル3選を徹底解説
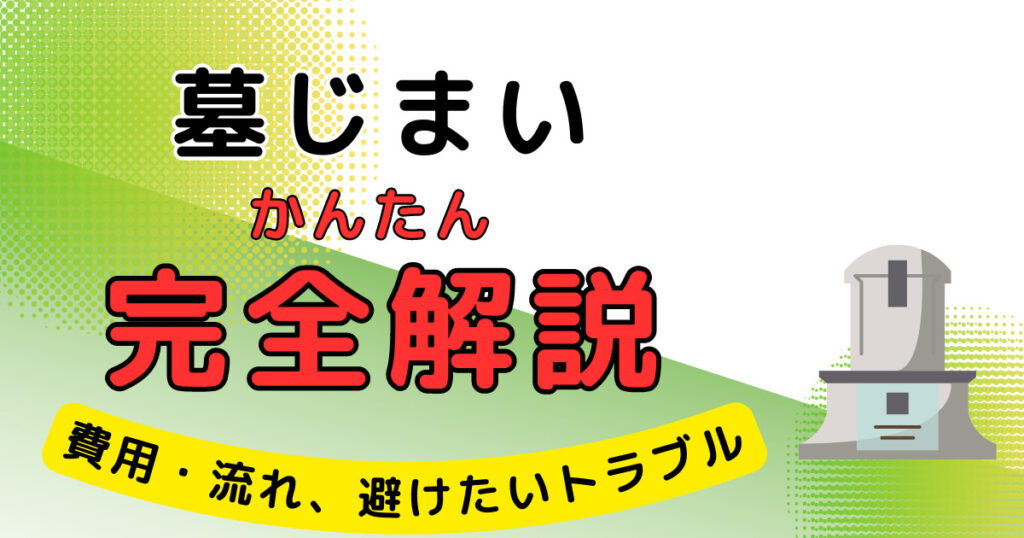
【結論】墓じまいの費用を誰が払う?→決まりがない→誰が払ってもOK

結論からお伝えすると、墓じまいの費用を誰が払うのか問題には、決まりがありません。
つまり、誰が払ってもOKですし、払わないといけない法律的義務もないのです。

あいまいすぎて困るんだけど…

あくまで”一般論”ですが…
一般的には、墓じまいの費用はお墓の名義人(継承者)が払うケースが多いです。
お墓の名義人には家の長男・長女がなっているケースがほとんどなので、長男・長女に費用負担が集中するケースが多いのです。

不公平すぎない…?
その通り、、、墓じまいの費用は「誰が払うのか」決まっていないので、
逆に言えば、兄弟姉妹・親族ふくめ、お墓の関係者全員で平等に費用を払うのが理想です。
そこで、墓じまいの費用を払うパターンを4つのケースとして紹介します。
祭祀継承者が払う
墓じまいの費用を払うのは、祭祀継承者になるケースがおおいです。
祭祀継承者とは、お墓の所有権を受け継いで祖先の供養をとりおこなう人のこと。
一般的には、家の長男・長女が祭祀継承者になることがおおいです。

資産に余裕のある方は問題ないかもしれませんが…
ご両親や兄弟姉妹、親族がいる場合、祭祀継承者のみで墓じまい費用を払うのは公平ではないですよね。
そこで以下のようなケースを想定しました。
祭祀継承者の両親に払ってもらう
墓じまいの費用は、高額になるケースがおおく、お墓の継承者だけで費用を払うのは困難です。
そのため、祭祀継承者の両親に費用を払ってもらうケースもあります。
子ども世代(現役世代)は、物価高や税金負担など生活負担もおおきいため、親世代が率先して「子どもの負担を減らしたい」と考え、費用を払うことも多いのです。

墓じまいの費用負担がすこし軽減されますね
兄弟姉妹と協力して払う
祭祀継承者に兄弟姉妹がいる場合は、全員平等で費用を負担するケースもあります。

筆者はこのパターンで墓じまい費用を払いました
”家”に関わる全員が向き合うべき「墓じまい」。
お墓の承継者など誰か一人だけが費用を払うのは、不公平です。
お墓の関係者それぞれの事情を考慮したうえで、なるべく平等に費用を払うのが合理的ですよね。

兄弟姉妹に費用負担を切り出しにくいなぁ…
いくら兄弟姉妹とはいえ、「墓じまいの費用を払ってほしい」と切り出すのは難しいかもしれません。
しかし逆に、費用負担をあいまいにしておくと、後々トラブルになったり、遺恨が残ることもあります。
各自の負担割合や金額などを明確にしておくことが重要ですね。
親族に一部を払ってもらう
先祖代々の遺骨が納められているお墓の場合、親族(=両親の兄弟姉妹)にも費用を払ってもらうケースもあります。
お墓の関係者全員で墓じまいの費用を払うのは、非常に合理的です。
ただし、墓じまいの費用を払う”法律的な決まり”がないのは事実。
「親戚なので費用を払って当然」というわけではありません。
あくまで、協力を仰ぐ形で費用負担を打診することをおすすめします。
(スポンサーリンク)
墓じまいの費用を誰が払う?|費用の内訳

墓じまいにかかる費用は30~250万円が相場です。
墓じまいの費用の内訳をまとめますね。
| 墓じまいの費用(内訳) | |
|---|---|
| 合計 | 30~250万円程度 |
| 墓石の解体・撤去 | 15万円~50万円程度 ※8~10万円/㎡程度 |
| 魂抜き | 3~10万円程度 |
| 離檀料 | 5~15万円程度 |
| 行政手続き | 数百円~1,000円程度 |
| 新しい供養先 | 5万円~150万円 |
墓石の解体・撤去

墓石の撤去・解体工事は15~50万円ほどが相場です。
1㎡(1m×1m)あたり8~15万円ほどが相場になる場合が一般的です。
しかし、墓地の立地や広さ、墓石の大きさによっても費用は変動します。
大規模な墓石の場合、撤去・解体にかかる石材店の人数、重機・特殊器具の使用有無によって高額になる可能性もあります。
魂抜き

魂抜きには3~10万円ほどの費用負担が発生します。
魂抜きとは、閉眼供養(へいがんくよう)または(へいげんくよう)とも呼ばれます。
お墓を解体・撤去する際、お墓に魂が残ったままでは工事できないので、「お墓から仏様の魂を抜くため」に魂抜きは必要不可欠なのです。
魂抜きを執り行う住職さんへ、感謝の気持ちとしてお布施をお渡しします。
離壇料

離壇料の相場は5~15万円ほどです。
離壇料が発生するのは、お寺の境内にお墓を立てている寺院墓地の場合です。
離檀料が発生する理由は、墓じまいを行うとお寺の檀家もやめることになるからです。
お寺の住職さんへ、これまでの感謝の気持ちとして包むお布施が離壇料なのです。
離壇料の相場に決まりはありませんが、離檀料を渡さないと、墓じまいがスムーズに進まないことがあるので、お寺とトラブルにならないよう細心の注意を払ってください。
なお、離檀料をはじめ、墓じまいのお布施の費用相場を下記記事でまとめています。
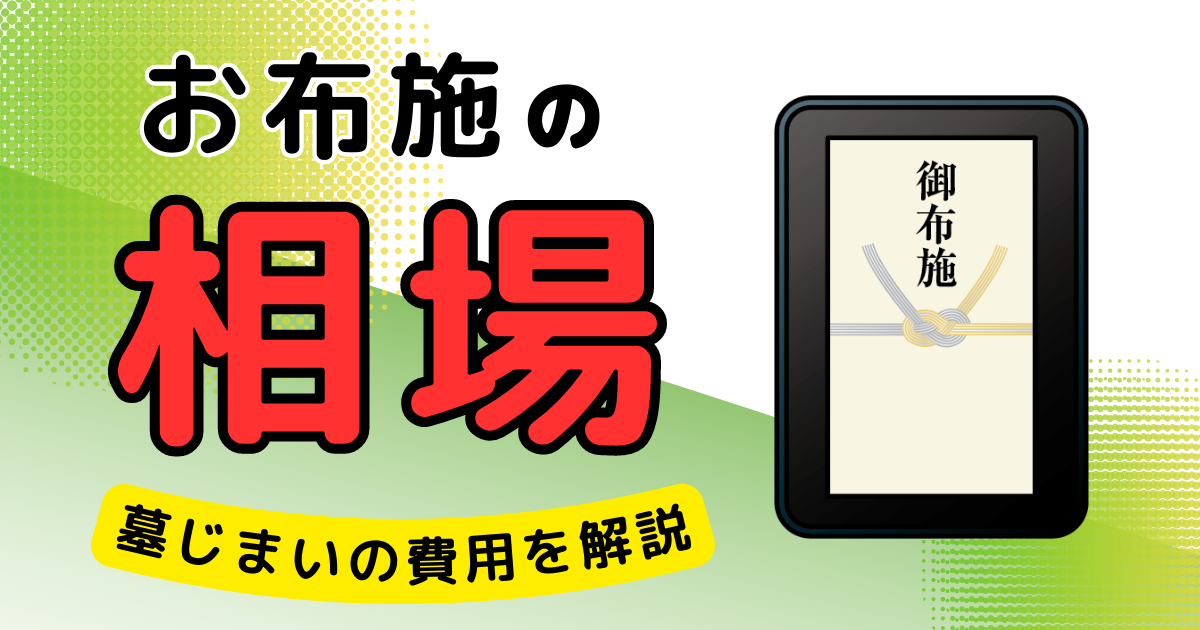
行政手続き

墓じまいの行政手続きにかかる費用は数百円~1,000円程度です。
墓じまいに必要な書類は下記のとおり。
| 墓じまい(改葬)に必要な書類 | |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 墓地のある自治体役所にて発行 |
| 埋蔵証明書 | 現在の墓地管理者が発行 |
| 受入証明書 | 新しい遺骨の埋葬先にて発行 |
| 承諾書 | 墓地のある自治体役所にて発行 ※墓地の使用者と改葬許可申請者が異なる場合 |
| 申請者の身分証明書写し | 書類の申請者の身分証明として発行 |
発行手数料はかからないことが多いですが、お墓のある自治体が遠方の場合、郵送費用などに費用がかかります。
(スポンサーリンク)
新しい供養先
お墓を解体・撤去すると、遺骨を新しい場所に移す必要があります。
供養先を新しくするための費用が5~150万円ほどです。
なお、新しい供養方法には下記のようなものがあります。
| 供養先を新しくする費用 | |
|---|---|
| 墓石のお墓 | 50~150万円 |
| 永代供養墓 | 10~100万円 |
| 合祀墓 | 3~30万円 |
| 納骨堂 | 30~100万円 |
| 樹木葬 | 10~100万円 |
| 散骨 | 5~30万円 |
| 手元供養 | 5~20万円 |
| 送骨 | 1~10万円 |
墓じまいの費用については下記記事でくわしく解説しています。
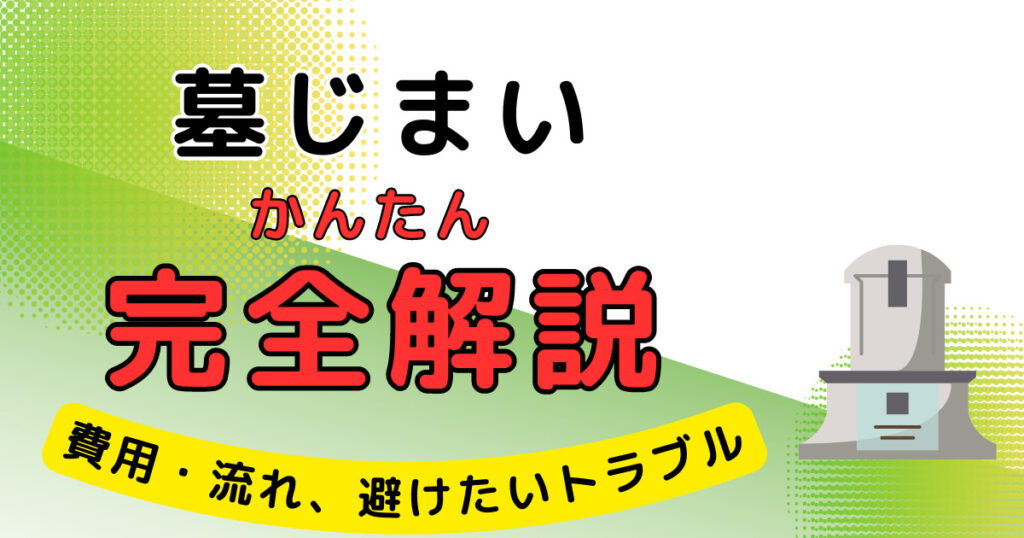
墓じまいの費用を払えないときの対処法

墓じまいの費用は30~250万円が相場なので、気軽に支払える金額ではないです。
ここでは、墓じまいの費用を払えないときの対処法を紹介します。
自治体の補助金制度を利用する
自治体のなかには墓じまいの補助金を受けられる地域があります。
自治体によって補助金額もかわりますし条件も違いますが、10~20万円ほどの補助金を受けられることが多いです。
ただし、墓じまいの補助金をもらえる自治体は全国でもごく少数。。。
対応している自治体が少ないのが残念なポイントです。
墓じまいの補助金のでる自治体はこちらで紹介しています。
メモリアルローンに申し込む
「メモリアルローン」とは、お墓の購入・撤去などに充てるお金を借りるためのローンです。
- 簡単に申し込める
- 使い道が限定されている
- 返済期間が長めに設定されている
- 一般的なローンより審査に通りやすい
- 金利が10%くらいに設定されている
メモリアルローンは銀行や大手の信販会社などで取り扱っています。
通常のローンより審査期間が短いため、急いでいる場合でも資金調達しやすいでしょう。
なお、墓じまいのメモリアルローンについては下記記事でもくわしく解説しています。
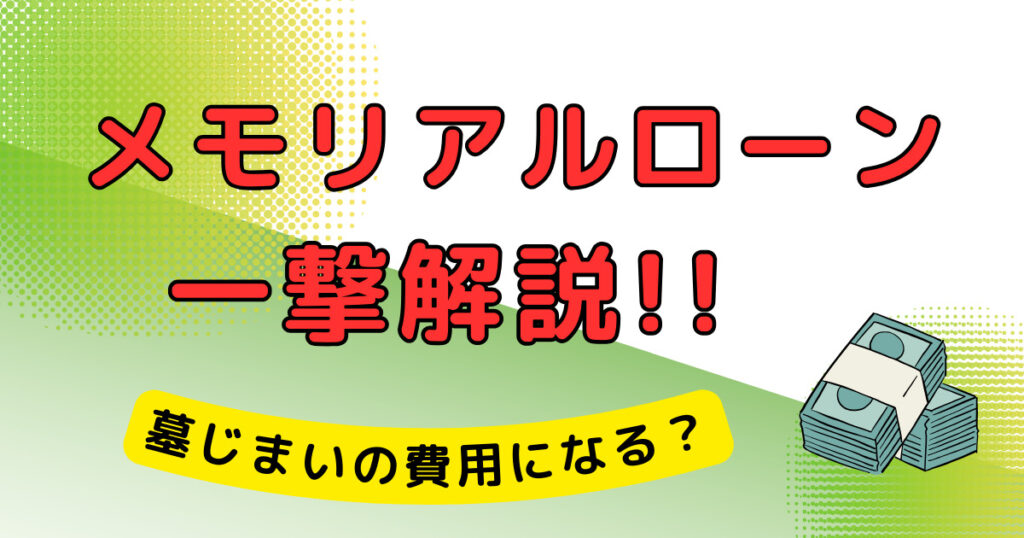
お寺や霊園に相談する
墓じまいの費用負担が厳しい場合は、お寺や霊園に相談することも検討しましょう。
なぜなら、墓じまいの費用には離檀料や法要も含まれ、数十万円にもおよぶケースも多いのです。
金銭的な事情がもとで墓じまいできないなら、お寺や霊園に方に、正直に打ち明けることで何かしら考慮してくれる可能性があります。
(スポンサーリンク)
墓じまいせず放置してしまったらどうなる?

墓じまいの費用を払えないからと、墓じまいせず放置してしまうとどうなるのでしょう?
下記2つのプロセスを経て、お墓が撤去されてしまいます。
管理費を請求されつづける
お墓の所有者は、寺院や墓地管理者に対して管理費を支払っています。
もし、墓じまいせずお墓を放置すると、管理費を今後ずっと請求されつづけることになります。
また、なかには管理費を払わない人もいますが、未払い分は必ず請求されるので気を付けてください。
無縁墓となり撤去される
墓じまいもせず、管理費も払わない状態がつづくと、お墓は無縁墓と呼ばれる状態になります。
無縁墓になったお墓は、一定期間経過すると管理者によって撤去されます。
※放置されたお墓は「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、墓地管理者によって撤去できるようになります。
なお、お墓が撤去された場合、取り出された遺骨は合祀墓(ごうしぼ)に埋葬されるのが一般的です。
墓じまいせずお墓を放置するとどうなるか?下記記事でもくわしく解説しています。
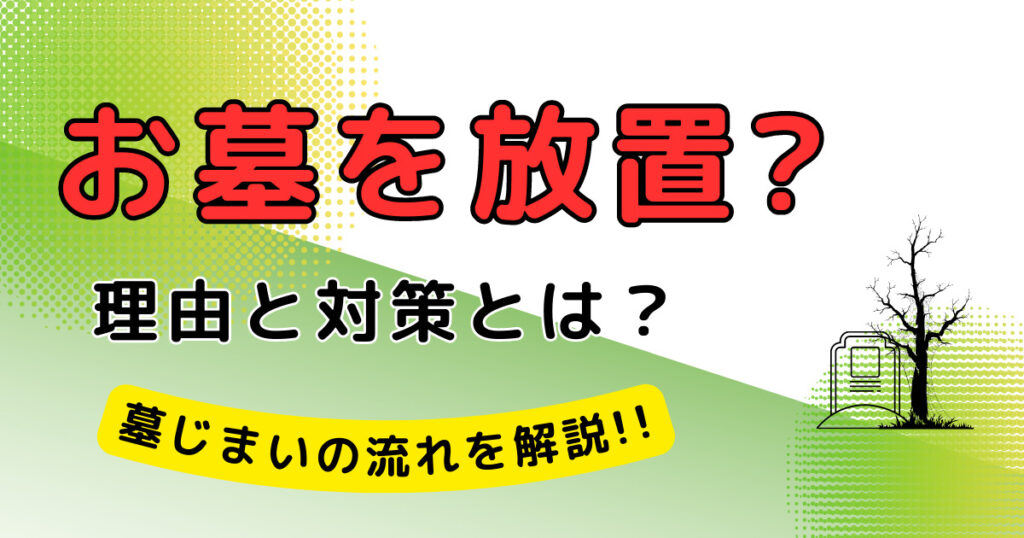
墓じまいの費用を抑えるコツ

墓じまいの費用は高額なので、できるだけ安く抑えたいと考える人は多いです。
ここでは墓じまいの費用を抑えるコツを紹介します。
複数の石材店から相見積もりをとる
墓石の解体・撤去工事について複数の石材店から相見積もりをとりましょう。
逆に、相見積もりをとらないと、地域の相場がわからなかったり、高額な石材店と契約してしまったりします。
ただし、指定石材店のある民間霊園や寺院墓地では石材店を選ぶ自由がないので、見積もりをとることができません。
費用の安い供養先をえらぶ
墓じまいしたあとの、遺骨の新しい供養方法によって費用が安くなります。
予算に応じて供養方法をえらぶことで、費用を抑えることが可能なのです。
なお、比較的費用の安い供養方法は合葬、散骨、送骨です。
下記記事では、墓じまいの費用を抑える方法をくわしく解説しているので参考にしてください。
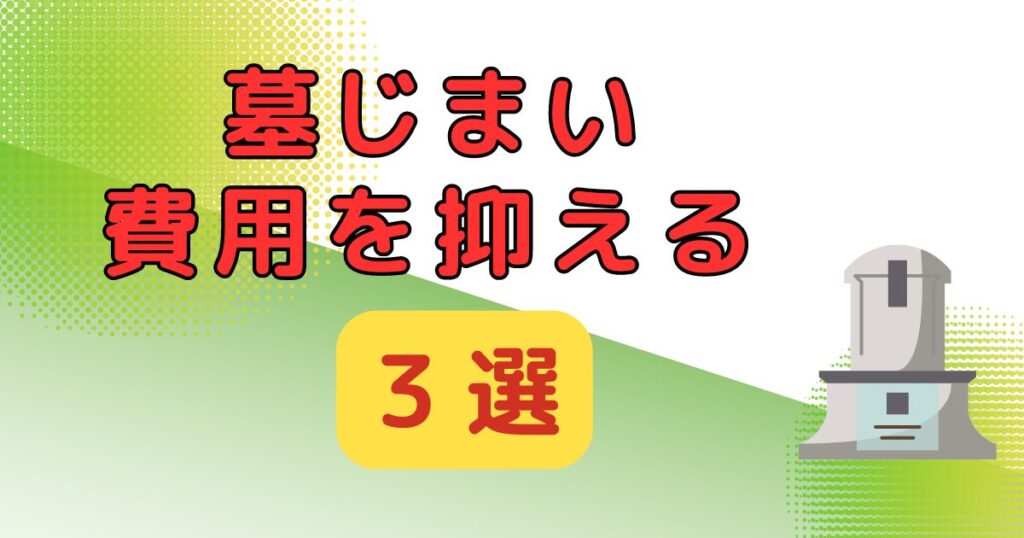
自治体の補助金を利用する
全国的に数は少ないですが、墓じまいの補助金制度を設定している自治体があります。
2024年現在、下記3か所の自治体で補助金をもらえることを確認できました。
| 補助金の出る自治体 | ||
|---|---|---|
| 浦安市 | 墓石撤去費等助成制度 | 浦安市公式サイト |
| 市川市 市川市霊園 | 市川市霊園 一般墓地返還促進事業 | 市川市公式サイト |
| 太田市 八王子山公園墓地 | 八王子山公園墓地 墓石撤去費用の助成金 | 太田市公式サイト |
最新の補助金情報については、補助金・助成金のポータルサイト「スマート補助金」を調べてください。
下記記事でも墓じまいで補助金をもらえる自治体や手続きを紹介しています。
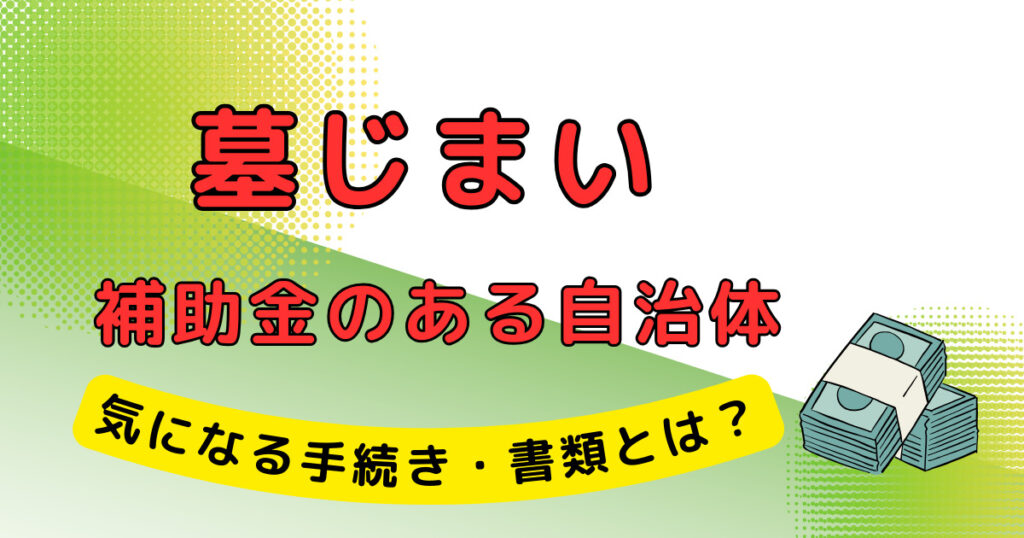
(スポンサーリンク)
墓じまいの費用は誰が払う?【まとめ】事前に話し合うことが重要

本記事では、墓じまいの費用を誰が払うのか、さまざまな角度から解説しました。
墓じまいには、30~250万円ほどの費用を払う必要がありますが、費用を誰が払うのか、法律的な決まりはありません。
つまり、費用は誰が払うのもOKですが、不公平にならないように家族・親族などで事前に話し合うことが重要です。
本記事で、「墓じまいの費用をどれくらい払うのか」「費用をやすく抑える方法があるのか」しっかり読んで、家族親族と話し合いの場を設けてみてください。
なお、下記記事では墓じまいとはなにか?費用や手続き・流れ、トラブル対策などを解説しています。